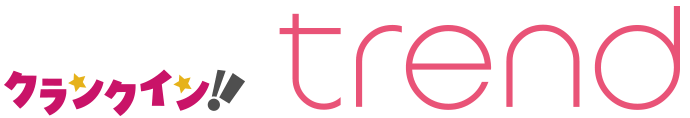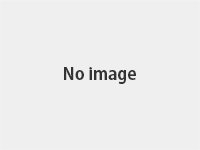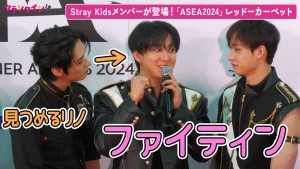小津安二郎
小津安二郎 出演映画作品
-
生れてはみたけれど
制作年:
小津安二郎のサイレント期の代表作であるばかりでなく、日本のサイレント映画の白眉として海外にまで広く知られた傑作。東京の郊外の新興住宅にサラリーマン一家が引っ越してきた。小学生の息子たちは早くも近所のガキ大将となり、金持ちの息子も子分として従えている。が、父親はその金持ちにペコペコと卑屈な態度ばかりとっている。その情けない父親の姿に耐えきれなくなった息子たちは、憤りを父親にぶつけるのだった……。前半の子供たちの実にユーモラスな描写から後半、父親をなじり大人の世界を告発する子供のシリアスなシーンへと一転。その躍動する画面はサイレントであることを忘れるほど。
-
お茶漬の味
制作年:
戦時中に検閲当局から却下された脚本を戦後になってから映画化。地方出身の商社マンが社長の親友の娘と結婚し、その夫婦が中年にさしかかった時の物語。妻は、旅行に野球観戦にと遊びまわり、夫のヤボったさや田舎者丸出しの習慣を嫌っていた。が、夫の海外出張をきっかけに、彼の頼もしさを見直す。夜中に二人でお茶漬けを食べながら、夫婦は人生はお茶漬けのようなものだと実感する。この作品では、飾らない生活がいちばんだと言う夫の考えを支える、庶民的な生活のディテールが、娯楽(パチンコ、競輪)、食べ物(トンカツ、ラーメン、漬物)、嗜好品(煙草の“朝日”)といったかたちでとり入れられている。若き日の川又昴が撮影助手を担当。
-
父ありき
制作年:
妻を失い、男手一つで息子を育ててきた男と、その父の平凡ではあるが、誠実な生き方を心から尊敬する息子の成長を追った物語。信州の地方都市の中学教師は、修学旅行先で生徒を一人溺死させてしまい、責任を感じて辞職。二人暮らしの息子を中学の寄宿舎に預けて一人上京する。やがて息子は成長し大学を出て、父親と同じように仙台で教員となる。父子は時々、温泉に出かけては再会を楽しんでいる。息子は、自分も東京に転職して一緒に暮らしたいと思うようになるが、父親に今の仕事を大事にしろと悟される……。父子で釣りをする有名なシーンをはじめ、小津を語る時に必ず引き合いに出される名作。
-
父ありき
制作年:
妻を失い、男手一つで息子を育ててきた男と、その父の平凡ではあるが、誠実な生き方を心から尊敬する息子の成長を追った物語。信州の地方都市の中学教師は、修学旅行先で生徒を一人溺死させてしまい、責任を感じて辞職。二人暮らしの息子を中学の寄宿舎に預けて一人上京する。やがて息子は成長し大学を出て、父親と同じように仙台で教員となる。父子は時々、温泉に出かけては再会を楽しんでいる。息子は、自分も東京に転職して一緒に暮らしたいと思うようになるが、父親に今の仕事を大事にしろと悟される……。父子で釣りをする有名なシーンをはじめ、小津を語る時に必ず引き合いに出される名作。
-
浮草物語
制作年:
池田忠雄=小津安二郎の名コンビによる人情ものの傑作。ドサ回りの一座の座長・喜八は、昔の女がいる田舎町に興行に行く。女には、喜八の子供がいて、立派に成長し、喜八をおじさんだと思い込まされている。一座の看板女優で、喜八の情婦でもある女は、昔の喜八の女に嫉妬して、妹分の女優に喜八の息子を誘惑するようにしむける。騒動が起こり、息子はおじさんだと思っていた喜八が実の父だと知ってしまう……。坂本武を主人公にしたいわゆる“喜八”ものの一作で、旅一座の哀感と、人々の細やかな心情とを小津安二郎ならではの淡々とした空間に描いた。1959年に小津自身が自ら「浮草」という題名でリメイクしている。
-
浮草物語
制作年:
池田忠雄=小津安二郎の名コンビによる人情ものの傑作。ドサ回りの一座の座長・喜八は、昔の女がいる田舎町に興行に行く。女には、喜八の子供がいて、立派に成長し、喜八をおじさんだと思い込まされている。一座の看板女優で、喜八の情婦でもある女は、昔の喜八の女に嫉妬して、妹分の女優に喜八の息子を誘惑するようにしむける。騒動が起こり、息子はおじさんだと思っていた喜八が実の父だと知ってしまう……。坂本武を主人公にしたいわゆる“喜八”ものの一作で、旅一座の哀感と、人々の細やかな心情とを小津安二郎ならではの淡々とした空間に描いた。1959年に小津自身が自ら「浮草」という題名でリメイクしている。
-
一人息子
制作年:
小津が初めて手掛けたトーキー作品。信州の田舎でたった一人の息子を進学させるために田畑を売り、身をけずって働いた母が、年老いてから東京の息子に会いにやって来る。だが、大学を出て出世していると思っていた息子は夜学の教師にすぎず、妻子とともに貧しい暮らしを送りながら将来への野心も失っていた……。小津が得意とする“親子”ものであるが、絶望的に暗いその世界は戦前の世相を反映していたのであろうか。全体的にトーキー1作目としては音に対する実験的な姿勢はみられず、あくまで現実音とセリフを使っただけのサイレント的演出で終始しており、小津スタイルの祖型となっている。
-
淑女は何を忘れたか
制作年:
いつも女房の尻に敷かれている大学教授の小宮が、突然大阪から上京してきた姪の節子に刺激され、発奮。口げんかをしても引き下がらず、初めて女房に平手打ちをくらわす。それ以来、夫婦の仲はかえって良くなるのだった……。小津安二郎のトーキー第2作。晩年の小津作品に頻出する、中年もしくは老年夫婦と、若い世代の娘の間の対立を含んだ信頼関係というテーマが、初めて大きく取り扱われた作品である。しかし、晩年のそれとは違い、全編に小津の西洋指向、モダニストぶりがあふれ、見事なソフィスティケイテッド・コメディとなっている。めったに雨の降らない小津作品中、これは珍しくも雨の降る一編。助監督で吉村公三郎が参加。
-
その夜の妻
制作年:
病気のわが子の治療費のために強盗を働いた夫。その夫を待ち続ける妻。そして夫を追う刑事。3者がほぼ一晩、アパートの一室で対峙していくという、小津安二郎監督がサイレント映画時代に撮ったサスペンス映画。アメリカ映画に傾倒していた小津監督ならではの洒落たモダニズム・タッチが妙味。一方で、ヒューマニズムの発露を怠っていないあたりも、この監督らしい秀作である。
-
麥秋〈1951年〉
制作年:
小津安二郎監督の力量が最も充実していた時期に作られた作品であり、「晩春」や「東京物語」など、小津の代表作と並べても決してひけをとらない素晴らしい出来で、小津の最高作とするファンも多い。戦前の小津のサイレント作品で数本の脚本を書いた野田高梧は、「晩春」以後小津との名コンビを続けていくのだが、そのセリフの間(ま)の絶妙さは本作で最大に発揮される。北鎌倉に住む間宮家の気がかりは、28歳になる独身娘・紀子の結婚だ。両親や兄夫婦は紀子の縁談についていろいろと心配するが、本人はあまり気のりでない様子。やがて兄妹のような気軽さでつきあっていた子持ちの男と結婚しようと紀子は決心する……。原節子、笠智衆をはじめ、相変わらず充実したキャストの存在感は大きいが、なかでも紀子の結婚相手の母を演じた杉村春子のコミカルさとシリアスさを使い分けた演技は抜群。
-
麥秋〈1951年〉
制作年:
小津安二郎監督の力量が最も充実していた時期に作られた作品であり、「晩春」や「東京物語」など、小津の代表作と並べても決してひけをとらない素晴らしい出来で、小津の最高作とするファンも多い。戦前の小津のサイレント作品で数本の脚本を書いた野田高梧は、「晩春」以後小津との名コンビを続けていくのだが、そのセリフの間(ま)の絶妙さは本作で最大に発揮される。北鎌倉に住む間宮家の気がかりは、28歳になる独身娘・紀子の結婚だ。両親や兄夫婦は紀子の縁談についていろいろと心配するが、本人はあまり気のりでない様子。やがて兄妹のような気軽さでつきあっていた子持ちの男と結婚しようと紀子は決心する……。原節子、笠智衆をはじめ、相変わらず充実したキャストの存在感は大きいが、なかでも紀子の結婚相手の母を演じた杉村春子のコミカルさとシリアスさを使い分けた演技は抜群。
-
お茶漬の味
制作年:
戦時中に検閲当局から却下された脚本を戦後になってから映画化。地方出身の商社マンが社長の親友の娘と結婚し、その夫婦が中年にさしかかった時の物語。妻は、旅行に野球観戦にと遊びまわり、夫のヤボったさや田舎者丸出しの習慣を嫌っていた。が、夫の海外出張をきっかけに、彼の頼もしさを見直す。夜中に二人でお茶漬けを食べながら、夫婦は人生はお茶漬けのようなものだと実感する。この作品では、飾らない生活がいちばんだと言う夫の考えを支える、庶民的な生活のディテールが、娯楽(パチンコ、競輪)、食べ物(トンカツ、ラーメン、漬物)、嗜好品(煙草の“朝日”)といったかたちでとり入れられている。若き日の川又昴が撮影助手を担当。
-
早春〈1956年〉
制作年:
小津作品としては、シリアスな感じの強い人間ドラマ。倦怠期の夫婦を描いた作品では、「お茶漬の味」などがあったが、それらは軽妙なユーモアを感じさせ、ほのぼのとしていた。ここでの夫婦の危機的状況はもっと深刻である。蒲田界隈に住む30歳の正二と昌子の夫婦の暮らしと、正二とサラリーマン仲間との交遊が並行して描かれる。夫の出征中に子供を病死させて以来、二人の仲は気まずく夫は無気力だ。そこへ夫の同僚の若い娘が関係してきて、夫婦間の不和が決定的となる。そんな状況から脱してヨリを戻し再出発を誓うシーンで映画は終わる。珍しく戦後派新世代の生活感を大胆に取り入れ、仕事仲間とのハイキングの小さな出来事がのっぴきならない不倫へと発展していくプロセスを、きめ細かく演出する。小津映画の珍しいキス・シーンに注目。
-
戸田家の兄妹
制作年:
父親を失ったブルジョワ一家で、残された妻と未婚の末娘が、結婚している息子や娘たちの家庭に次々に世話になるが、どこでも厄介者扱いされ、仕方なく二人は古ぼけた別荘に住むことになる。だが、亡父の一周忌に親類一同が集まった席上で、満州から帰国した末の弟が、兄や姉たちの母と末娘に対する仕打ちを知り、憤って激しく罵倒する。そして母と妹を満州に連れていくことにする……。戦時下の作品であり、その物語は当時の情勢に迎合した感じもあるが、端的な演出で高い評価を得た。また、小津と名コンビを組むことになる厚田雄春(当時は厚田雄治)が初めて正カメラマンとしてついた作品でもある。
-
早春〈1956年〉
制作年:
小津作品としては、シリアスな感じの強い人間ドラマ。倦怠期の夫婦を描いた作品では、「お茶漬の味」などがあったが、それらは軽妙なユーモアを感じさせ、ほのぼのとしていた。ここでの夫婦の危機的状況はもっと深刻である。蒲田界隈に住む30歳の正二と昌子の夫婦の暮らしと、正二とサラリーマン仲間との交遊が並行して描かれる。夫の出征中に子供を病死させて以来、二人の仲は気まずく夫は無気力だ。そこへ夫の同僚の若い娘が関係してきて、夫婦間の不和が決定的となる。そんな状況から脱してヨリを戻し再出発を誓うシーンで映画は終わる。珍しく戦後派新世代の生活感を大胆に取り入れ、仕事仲間とのハイキングの小さな出来事がのっぴきならない不倫へと発展していくプロセスを、きめ細かく演出する。小津映画の珍しいキス・シーンに注目。
-
朗かに歩め
制作年:
“ナイフの謙”と呼ばれるヤクザな若者は、ある日タイピストのやす江に一目惚れしてしまう。ふとしたことからやす江の妹、みつ子と知り合った謙は、3人でピクニックに出かける。ヤクザとは知らず謙に心惹かれていくやす江だが……。アメリカ映画に心酔していた小津安二郎が、バタ臭い設定で描いた、サイレンとの人情喜劇。
-
淑女と髯
制作年:
大学の剣道部主将・岡島は、そのヒゲ面が災いして就職試験に落ちても全く動じることのない剛の者。しかし、あるオフィスガールに忠告されてヒゲを剃ってみたら、一転してスマートな二枚目と化してしまい、周囲の女性たちからモテモテの存在となっていくが……。サイレント映画時代の小津安二郎監督が最も得意としたナンセンス喜劇の代表格ともいえる秀作。
-
小早川家の秋
制作年:
主として松竹で映画を作ってきた小津が、珍しく東宝で、しかも東宝主演級の俳優を多数出演させ撮り上げた作品である。造り酒屋の小早川万兵衛を中心に、小早川家にかかわる人々の悲喜こもごもを独特の情感で描写している。万兵衛の死んだ長男の嫁・秋子を再婚させようと、親戚連中は手を尽くすが、秋子はなかなか承諾しない。次女・紀子は転勤した同僚への恋を断ち切れずにいる。一方、妻に先立たれた万兵衛は、昔なじみの妾とよりを戻し、人目を盗んでは通い詰めていた。妻の法事の日の夜、急に倒れる万兵衛。一時は回復するが数日後、妾の家でぽっくり逝ってしまう。親戚一同が会し、静かな葬式が営まれる。火葬場の煙突のけむりを人々がそれぞれの思いを抱いて見上げる名シーンの記憶が、伊丹十三監督の処女作「お葬式」に反映した。
-
小早川家の秋
制作年:
主として松竹で映画を作ってきた小津が、珍しく東宝で、しかも東宝主演級の俳優を多数出演させ撮り上げた作品である。造り酒屋の小早川万兵衛を中心に、小早川家にかかわる人々の悲喜こもごもを独特の情感で描写している。万兵衛の死んだ長男の嫁・秋子を再婚させようと、親戚連中は手を尽くすが、秋子はなかなか承諾しない。次女・紀子は転勤した同僚への恋を断ち切れずにいる。一方、妻に先立たれた万兵衛は、昔なじみの妾とよりを戻し、人目を盗んでは通い詰めていた。妻の法事の日の夜、急に倒れる万兵衛。一時は回復するが数日後、妾の家でぽっくり逝ってしまう。親戚一同が会し、静かな葬式が営まれる。火葬場の煙突のけむりを人々がそれぞれの思いを抱いて見上げる名シーンの記憶が、伊丹十三監督の処女作「お葬式」に反映した。
-
宗方姉妹
制作年:
『朝日新聞』に連載された長編小説を、松竹の名匠・小津が新東宝の資本で撮り上げた文芸作品。小津が得意とする平坦な日常感覚のリズムを刻む物語とは幾分趣を異にし、原作ものらしいドラマティックな展開が特徴。日本の古い習慣に準じて生きる姉と、束縛されず自由に生きる妹を対照的に描きながら、日本の社会を浮き彫りにしている。夫・亮助が失業し、やむなくバー勤めをする妻・節子。亮助は自信をなくし、暗く心を閉ざしている。夫のある身でありながら、姉がひそかに神戸の家具屋・田代に想いを寄せているのを知る妹・満里子は気が気でない。亮助、田代、そして姉に、満里子は正直な気持ちをぶつけていく。
-
宗方姉妹
制作年:
『朝日新聞』に連載された長編小説を、松竹の名匠・小津が新東宝の資本で撮り上げた文芸作品。小津が得意とする平坦な日常感覚のリズムを刻む物語とは幾分趣を異にし、原作ものらしいドラマティックな展開が特徴。日本の古い習慣に準じて生きる姉と、束縛されず自由に生きる妹を対照的に描きながら、日本の社会を浮き彫りにしている。夫・亮助が失業し、やむなくバー勤めをする妻・節子。亮助は自信をなくし、暗く心を閉ざしている。夫のある身でありながら、姉がひそかに神戸の家具屋・田代に想いを寄せているのを知る妹・満里子は気が気でない。亮助、田代、そして姉に、満里子は正直な気持ちをぶつけていく。
-
東京物語
制作年:
黒澤明、溝口健二とともに日本を代表する映画作家・小津安二郎の代表作といえばこの「東京物語」につきるだろう。小津がサイレント期から描き続けてきた親子関係のテーマの集大成ともいえる作品である。地方から老いた夫婦が上京し、成人した子供たちの家を訪ねる。子供たちははじめは歓迎するが、やがて両親がじゃまになって熱海に行かせたりして厄介ばらい。戦死した息子のアパート住まいの未亡人だけが親身になって面倒をみてくれるという皮肉。やがて老夫婦は田舎に帰るが、その直後、妻は急死してしまう。一人残された老人は、静かに海を見つめて……。戦後の日本における家族生活の崩壊を描いた、と監督本人が語るこの作品は、人間の孤独感、死生観といったテーマまでをも取り込み、味わい深い作品となった。志賀直哉を深く愛した小津監督は、『暗夜行路』にちなんで尾道市をラスト・シークエンスの舞台に選んだが、その尾道の寂れて、どこか温かい風景が、この厳しいテーマを繊細に包み込み、忘れることのできない画面を生み出した。
-
東京物語
制作年:
黒澤明、溝口健二とともに日本を代表する映画作家・小津安二郎の代表作といえばこの「東京物語」につきるだろう。小津がサイレント期から描き続けてきた親子関係のテーマの集大成ともいえる作品である。地方から老いた夫婦が上京し、成人した子供たちの家を訪ねる。子供たちははじめは歓迎するが、やがて両親がじゃまになって熱海に行かせたりして厄介ばらい。戦死した息子のアパート住まいの未亡人だけが親身になって面倒をみてくれるという皮肉。やがて老夫婦は田舎に帰るが、その直後、妻は急死してしまう。一人残された老人は、静かに海を見つめて……。戦後の日本における家族生活の崩壊を描いた、と監督本人が語るこの作品は、人間の孤独感、死生観といったテーマまでをも取り込み、味わい深い作品となった。志賀直哉を深く愛した小津監督は、『暗夜行路』にちなんで尾道市をラスト・シークエンスの舞台に選んだが、その尾道の寂れて、どこか温かい風景が、この厳しいテーマを繊細に包み込み、忘れることのできない画面を生み出した。
-
お早よう
制作年:
松竹の伝統である下町喜劇、長屋喜劇の舞台を郊外の建売住宅地に移した、小津のユーモアセンスの冴えわたった傑作。10軒ほどの家が建ち並ぶ住宅地に住む人々ののどかな日々をスケッチ風に描写。小津安二郎が多くとり上げた、親子、兄弟、夫婦間の葛藤というテーマはここではそれほど深く堀り下げられることはなく、タイトルのように日常のあいさつや平凡な会話を通し、庶民の生活がいきいきと浮かんでくる。「生れてはみたけれど」を思わせる兄弟が登場して、いたずらしたり、父親にテレビをねだったり……。最後にテレビを買ってもらった弟が唐突にまわすフラフープのおかしさ!
-
風の中の牝鷄
制作年:
第二次大戦中に外地に行ったきり、戦争が終わっても帰って来ない雨宮。妻・時子はその間、なんとか苦しい生活をやりくりしていたが、子供が入院してしまい、ついに経済的に破綻。一夜だけ売春する。やがて戻ってきた雨宮は、ある日その事実を知って……。夫婦の心情的危機状況を、とことんシリアスに描ききった、小津の戦後第2作。どんなシリアスな状況を描く時でも常にアクションやセリフのギャグを盛り込み、軽みのきいた作品に仕上げてきた小津映画の中で、これは「東京暮色」とともに、異色中の異色ともいえる出来ばえ。小津の画面に一度たりとも姿を現さなかった階段が、本作で初めて真正面から登場。小津全作品中唯一のバイオレンス・シーンが展開される。その即物的な暴力描写には誰もが息を呑まされるはず。なお本作は、小津が野田高梧以外の脚本家とコンビを組んだ最後の作品としても記憶されるべきだろう。
-
戸田家の兄妹
制作年:
父親を失ったブルジョワ一家で、残された妻と未婚の末娘が、結婚している息子や娘たちの家庭に次々に世話になるが、どこでも厄介者扱いされ、仕方なく二人は古ぼけた別荘に住むことになる。だが、亡父の一周忌に親類一同が集まった席上で、満州から帰国した末の弟が、兄や姉たちの母と末娘に対する仕打ちを知り、憤って激しく罵倒する。そして母と妹を満州に連れていくことにする……。戦時下の作品であり、その物語は当時の情勢に迎合した感じもあるが、端的な演出で高い評価を得た。また、小津と名コンビを組むことになる厚田雄春(当時は厚田雄治)が初めて正カメラマンとしてついた作品でもある。
-
東京の宿
制作年:
坂本武を主人公にした人情劇、“喜八もの“の一編。失業した父が二人の子供を連れ、工場地帯を職を求めて歩き回る。次々に門前払いを食った父子は、安宿に転がり込み、同じ放浪の身にある母娘に出会う……。深刻な失業問題を取り上げ、殺伐とした風景の中に人間の孤独感や絶望をしみ出させた作品。
-
学生ロマンス 若き日
制作年:
現存する小津安二郎の作品の中では最も古い作品。一般的に小津作品は、後期の印象からローアングル、固定画面のスタイルで広く知られているが、この「若き日」をはじめとする初期の作品群にはまったく違った小津のスタイルが散りばめられている。冒頭、主人公たちの住む早稲田の学生下宿を映しだすまで、カメラがパンにつぐパンを繰り返し、目まぐるしいまでのスピード感を生むさまを見れば、後期の小津作品しか知らないファンは目を丸くすることだろう。S大学に通う学生・渡辺の住む下宿には“2階貸間”の札が貼ってある。渡辺は、なんとか2階にきれいな女性が入って知り合いになれないものかと、やきもきする毎日。そこへ千恵子という美人がやって来た。渡辺は強引に千恵子と知り合いになるや、彼女が赤倉にスキーに行くことを聞き出し、自分も友人の山本とともにスキーに出かけることにするが……。キートン、ロイドなどのアメリカン・コメディ映画を下敷きにして、たたみかけるようなテンポで展開する爆笑ものの一編だ。
-
秋日和
制作年:
小津安二郎作品の家族劇では娘役として欠かせない存在であった女優・原節子が母親役に回った、小津晩年の傑作。夫を失ったばかりの秋子は、亡夫の友人たちに再婚を勧められる。彼女にはその気はないが、まだ美しい未亡人である母親が再婚するのではないかと、娘のアヤ子は気が気でない。母親の気持ちを誤解した娘は反抗し始める。やがて二人は和解し、いつの日か嫁いでいく娘をつれて秋子はささやかな二人きりの旅行に出かける……。亡夫の友人を演じた佐分利信、北竜二、中村伸郎のとぼけたやりとりがおかしく、岡田茉莉子の初々しさも印象深いが、何より母娘旅行のシーンの優しさが心にしみる。
-
秋日和
制作年:
小津安二郎作品の家族劇では娘役として欠かせない存在であった女優・原節子が母親役に回った、小津晩年の傑作。夫を失ったばかりの秋子は、亡夫の友人たちに再婚を勧められる。彼女にはその気はないが、まだ美しい未亡人である母親が再婚するのではないかと、娘のアヤ子は気が気でない。母親の気持ちを誤解した娘は反抗し始める。やがて二人は和解し、いつの日か嫁いでいく娘をつれて秋子はささやかな二人きりの旅行に出かける……。亡夫の友人を演じた佐分利信、北竜二、中村伸郎のとぼけたやりとりがおかしく、岡田茉莉子の初々しさも印象深いが、何より母娘旅行のシーンの優しさが心にしみる。
-
大人の見る絵本 生れてはみたけれど
制作年:
東京郊外に引っ越してきた吉井一家。二人の子供たちはすぐに近所の子供たちと喧嘩を繰り返してガキ大将的存在となっていくが、ある日二人は自分たちに厳格な父親が上司にこびまくっている姿を捉えた8ミリ映画を見てしまい……。小津安二郎監督のサイレント映画時代の代表作。子供たちが繰り広げるユーモラスな描写と、当時の深刻な社会不況とを両立させた傑作である。
-
彼岸花
制作年:
小津安二郎が手掛けた初めてのカラー作品。田中絹代・有馬稲子・山本富士子の豪華な女優陣を配して、相変わらずの小津調ホーム・ドラマで楽しめる。がんこな父・佐分利信は、父に相談なしで結婚相手を決めてしまったことに腹をたて、娘の結婚を許さないと言いだす。一方、知人の娘から自由な恋愛結婚についての意見を求められ賛成してしまう。そんな矛盾だらけでありながら、自分の娘のことになると冷静になれない父親像がおかしく、その妻・田中絹代が夫と娘を和解させようとひと苦労。里見惇の原作を小津安二郎・野田高梧の名脚本コンビが脚色した佳作である。
-
彼岸花
制作年:
小津安二郎が手掛けた初めてのカラー作品。田中絹代・有馬稲子・山本富士子の豪華な女優陣を配して、相変わらずの小津調ホーム・ドラマで楽しめる。がんこな父・佐分利信は、父に相談なしで結婚相手を決めてしまったことに腹をたて、娘の結婚を許さないと言いだす。一方、知人の娘から自由な恋愛結婚についての意見を求められ賛成してしまう。そんな矛盾だらけでありながら、自分の娘のことになると冷静になれない父親像がおかしく、その妻・田中絹代が夫と娘を和解させようとひと苦労。里見惇の原作を小津安二郎・野田高梧の名脚本コンビが脚色した佳作である。
-
浮草
制作年:
ほとんどの作品を松竹で撮った小津安二郎監督が大映で撮った唯一の作品。溝口健二と“いつか大映で1本撮る”と約束していたという。撮影もずっと一緒に仕事をしてきた厚田雄春ではなく、溝口作品には欠かせないカメラマン・宮川一夫を起用。戦前の1934年に同監督が撮った「浮草物語」のリメイクである。ドサ回りの芝居の座長が昔の女のいる田舎町に巡業に。その女には座長が生ませた子供がいるが、その子は座長をおじさんだと思っている。しかし、座長の情婦である女優が昔の女に嫉妬、妹分の女優に座長の息子を誘惑させる。京マチ子の情念むきだしの演技も小津世界にうまく溶け込んで印象的。
-
浮草
制作年:
ほとんどの作品を松竹で撮った小津安二郎監督が大映で撮った唯一の作品。溝口健二と“いつか大映で1本撮る”と約束していたという。撮影もずっと一緒に仕事をしてきた厚田雄春ではなく、溝口作品には欠かせないカメラマン・宮川一夫を起用。戦前の1934年に同監督が撮った「浮草物語」のリメイクである。ドサ回りの芝居の座長が昔の女のいる田舎町に巡業に。その女には座長が生ませた子供がいるが、その子は座長をおじさんだと思っている。しかし、座長の情婦である女優が昔の女に嫉妬、妹分の女優に座長の息子を誘惑させる。京マチ子の情念むきだしの演技も小津世界にうまく溶け込んで印象的。
-
暖春
制作年:
故・小津安二郎が生前親しかった里見惇と共作した原作を、大船調の後継者・中村登が脚色・監督した。京都・南禅寺界隈で小料理屋を営む母と、婚期に差しかかった娘をめぐるホームドラマ。母の望む男と結婚するまでの様々な葛藤と和解を描く。
-
出来ごころ
制作年:
坂本武演じる、どこか頼りないが人情には厚い男、喜八を主人公にした作品が小津安二郎には多くあり、いわいる“喜八もの”と呼ばれているが、この「出来ごころ」はその第1作にあたる。小津は、サイレント期はナンセンスなドタバタ・コメディを多く手掛け、後期は家族の人間関係を中心に独自のドラマを生み出したが、この“喜八もの”はその過度期にあたるといえるだろう。長屋に住む気のいい男、喜八は、ある日いわくありげな少女・春江が道をさ迷っているのを見つけ、めし屋のおかみに預ける。喜八とその相棒、次郎は次第に春江に心惹かれていく。小津の中期を代表する名作である。
-
東京の合唱
制作年:
勤め先の保険会社をクビになった同僚に同情し会社に抗議、自らもクビとなってしまった岡島。やがて彼は、街で偶然出会った母校の恩師・大村の世話で、彼が学校退職後に始めたカレー屋“カロリー軒”を手伝うことになるが……。小津安二郎が、それまでのハリウッド映画完全再現指向を捨て、日本の風土の中でそのテクニックを充分に生かし始めた、転換点とでもいうべき作品。退職した元教師が東京で料理屋を開き、そこでかつての教え子の世話をするというのは、小津作品にしばしば現れるパターンである。
-
学生ロマンス 若き日
制作年:
現存する小津安二郎の作品の中では最も古い作品。一般的に小津作品は、後期の印象からローアングル、固定画面のスタイルで広く知られているが、この「若き日」をはじめとする初期の作品群にはまったく違った小津のスタイルが散りばめられている。冒頭、主人公たちの住む早稲田の学生下宿を映しだすまで、カメラがパンにつぐパンを繰り返し、目まぐるしいまでのスピード感を生むさまを見れば、後期の小津作品しか知らないファンは目を丸くすることだろう。S大学に通う学生・渡辺の住む下宿には“2階貸間”の札が貼ってある。渡辺は、なんとか2階にきれいな女性が入って知り合いになれないものかと、やきもきする毎日。そこへ千恵子という美人がやって来た。渡辺は強引に千恵子と知り合いになるや、彼女が赤倉にスキーに行くことを聞き出し、自分も友人の山本とともにスキーに出かけることにするが……。キートン、ロイドなどのアメリカン・コメディ映画を下敷きにして、たたみかけるようなテンポで展開する爆笑ものの一編だ。
-
東京暮色
制作年:
二人の娘を残したまま、母親が愛人と家出をしてしまった一家の物語で、戦後期の小津のフィルモグラフィーでは例外的に暗く、陰うつな雰囲気に包まれた異色の作品といえるだろう。しっかり者の姉、つまらぬボーイフレンドに妊娠させられ事故死する妹、妻に逃げられながら態度がはっきりしない父親、変転の果てに、ひっそりと麻雀荘を営む母親。小津監督は、それぞれのもの言わぬ肩や背中に生きることの悲哀をずっしりと感じさせ、寂漠の人生模様を甘い感傷に溺れることなく、見事に織り上げてみせた。とりわけ、母親と娘の再度の別れのシークエンスが激しく胸を打つ。
-
秋刀魚の味
制作年:
巨匠・小津安二郎の遺作となった作品。小津自身は家庭を持たず、母と二人きりの生活を送ってきたのだが、その母をこの「秋刀魚の味」の構想中に失った。娘を嫁に出した父、あるいは母の孤独というのは小津作品に繰り返し現れるシチュエーションだが、真の孤独を味わった小津によって描かれたこの作品での父親役・笠智衆の、淋しさに震える背中は今までにないすご味がある。娘と暮らす初老のサラリーマンは、婚期の娘の結婚を心配する。娘には好きな相手がいるらしいが、はっきりしない。父は、同僚から娘の見合いを勧められる。縁談はもたつきながらやがてまとまり、娘は嫁いでいく……。どちらかといえば、軽いコメディ・タッチで作られているところが、逆に父親の孤独感を浮き彫りにして秀逸である。娘を演じた岩下志麻の快活さも新鮮で、原節子が演じてきたしっとりした感じとは違った味わいがある。この作品を最後に翌年、小津は60才の誕生日にその生涯を閉じた。
-
秋刀魚の味
制作年:
巨匠・小津安二郎の遺作となった作品。小津自身は家庭を持たず、母と二人きりの生活を送ってきたのだが、その母をこの「秋刀魚の味」の構想中に失った。娘を嫁に出した父、あるいは母の孤独というのは小津作品に繰り返し現れるシチュエーションだが、真の孤独を味わった小津によって描かれたこの作品での父親役・笠智衆の、淋しさに震える背中は今までにないすご味がある。娘と暮らす初老のサラリーマンは、婚期の娘の結婚を心配する。娘には好きな相手がいるらしいが、はっきりしない。父は、同僚から娘の見合いを勧められる。縁談はもたつきながらやがてまとまり、娘は嫁いでいく……。どちらかといえば、軽いコメディ・タッチで作られているところが、逆に父親の孤独感を浮き彫りにして秀逸である。娘を演じた岩下志麻の快活さも新鮮で、原節子が演じてきたしっとりした感じとは違った味わいがある。この作品を最後に翌年、小津は60才の誕生日にその生涯を閉じた。
-
母を恋はずや
制作年:
大黒柱の父親が急死し、経済的に没落せざるを得ない母子家庭の生活は、日ごとに厳しくなっていく。やがて母の愛情が不公平であることに気づいた兄は、弟や母とけんかして家を出る。だが兄は実は亡き父の前妻との間の子だった……。母子の愛情を、小津特有の細やかな画面の中に描ききった秀作。現存フィルムには欠落部分がある。
-
非常線の女
制作年:
アメリカ映画に大きく影響を受けた小津安二郎が撮った和製ギャング映画。衣装、美術など、どこを見てもアメリカ映画そのもので主役の岡譲二のバタ臭い容貌も日本映画にはない味を出している。肝心のヒロイン、田中絹代だけがこれ以上ない日本的な顔をしているのはご愛嬌か。タイピストの時子は社長令息から高価な指輪を贈られるが、彼女には他に恋人があった。街のチンピラを取り仕切るボクサーくずれの襄二である。ある日、襄二はかたぎの娘・和子と知り合い、心惹かれる。時子は嫉妬に燃え始め……。長く忘れられていた作品だが小津を語るうえで必見だ。
-
東京の女
制作年:
大学予科生の良一は、一緒に暮らす姉のちか子に月謝と小遣いをもらって学校に通っている。ちか子は弟のために昼はタイピスト、夜は翻訳の手伝いをして働いているのだ。だがある日、姉がいかがわしい酒場に勤めているという噂が良一の耳に……。登場人物を徹底的に切り詰めた室内心理劇で細かい描写が印象的。
-
青春の夢いまいづこ
制作年:
学生時代に親友同士だった哲夫と一郎は、社会に出ると皮肉なことに雇用主とそこで働く使用人という立場におかれる。やがて二人は一人の娘をめぐって三角関係に落ちるが……。小津得意の“カレッジ・コメディ”の味を残しながら、哲夫が一郎を殴り続ける激烈なシーンもあり、小津の転換期にあたる作品である。
-
晩春
制作年:
小津安二郎といえば、父と娘、あるいは母と娘など、平凡な家庭の日常を淡々と描いた作風で知られた作家だが、実はそういう家族劇は後期、脚本家の野田高梧と組んだ頃のものであり、初期にはギャング映画やコメディなど様々なジャンルを手掛けていた。そんな後期の小津スタイルが確立されたのがこの「晩春」である。北鎌倉に住む大学教授は、婚期を逃がしかけている娘を結婚させようとする。父を一人にはしたくないと、娘は結婚に乗り気ではないが、父は寂しさをこらえて娘を嫁がせるのだった……。父娘二人が、最後に水入らずで枕を並べて過ごす夜のシーンは特に有名で、壷の空ショットが挿入されることから“壷のシーン”として多くの評論家にとり上げられ、研究されてきた。余計なセリフや感情表現を用いず、その場の空気ですべてを語ってしまう小津演出の真髄がここにある。
-
晩春
制作年:
小津安二郎といえば、父と娘、あるいは母と娘など、平凡な家庭の日常を淡々と描いた作風で知られた作家だが、実はそういう家族劇は後期、脚本家の野田高梧と組んだ頃のものであり、初期にはギャング映画やコメディなど様々なジャンルを手掛けていた。そんな後期の小津スタイルが確立されたのがこの「晩春」である。北鎌倉に住む大学教授は、婚期を逃がしかけている娘を結婚させようとする。父を一人にはしたくないと、娘は結婚に乗り気ではないが、父は寂しさをこらえて娘を嫁がせるのだった……。父娘二人が、最後に水入らずで枕を並べて過ごす夜のシーンは特に有名で、壷の空ショットが挿入されることから“壷のシーン”として多くの評論家にとり上げられ、研究されてきた。余計なセリフや感情表現を用いず、その場の空気ですべてを語ってしまう小津演出の真髄がここにある。
-
長屋紳士録
制作年:
太平洋戦争後の映画界では軍部による統制が解かれ、軍政批判の題材を取り上げる映画作家が続出したが、小津はそんな風潮には迎合せず、サイレント期の「出来ごころ」「浮草物語」「東京の宿」などの坂本武を主人公とした“喜八”ものを取り上げた。だがここでは喜八本人はむしろ脇役で、相手役の“かあやん”が主人公となっている。荒廃した焼け野原の東京を舞台に、親にはぐれてしまった子供が長屋に連れて来られる。人々はグチをこぼしながらも次第にその子供と情が通じるようになり、やがてその子は長屋になくてはならない人気者になる。しかしある日子供の父親が姿を現した……。ほのぼのとした人情とユーモアにあふれる作品であり、小津安二郎監督の作品のなかでも、最も温かい感情に満ちた一編と言える。笠智衆ら長屋の連中が酔っぱらって“のぞきからくり”の口上を歌いはじめるシーンのにぎやかな盛り上がりは抱腹絶倒もの。
-
長屋紳士録
制作年:
太平洋戦争後の映画界では軍部による統制が解かれ、軍政批判の題材を取り上げる映画作家が続出したが、小津はそんな風潮には迎合せず、サイレント期の「出来ごころ」「浮草物語」「東京の宿」などの坂本武を主人公とした“喜八”ものを取り上げた。だがここでは喜八本人はむしろ脇役で、相手役の“かあやん”が主人公となっている。荒廃した焼け野原の東京を舞台に、親にはぐれてしまった子供が長屋に連れて来られる。人々はグチをこぼしながらも次第にその子供と情が通じるようになり、やがてその子は長屋になくてはならない人気者になる。しかしある日子供の父親が姿を現した……。ほのぼのとした人情とユーモアにあふれる作品であり、小津安二郎監督の作品のなかでも、最も温かい感情に満ちた一編と言える。笠智衆ら長屋の連中が酔っぱらって“のぞきからくり”の口上を歌いはじめるシーンのにぎやかな盛り上がりは抱腹絶倒もの。
-
東京暮色
制作年:
二人の娘を残したまま、母親が愛人と家出をしてしまった一家の物語で、戦後期の小津のフィルモグラフィーでは例外的に暗く、陰うつな雰囲気に包まれた異色の作品といえるだろう。しっかり者の姉、つまらぬボーイフレンドに妊娠させられ事故死する妹、妻に逃げられながら態度がはっきりしない父親、変転の果てに、ひっそりと麻雀荘を営む母親。小津監督は、それぞれのもの言わぬ肩や背中に生きることの悲哀をずっしりと感じさせ、寂漠の人生模様を甘い感傷に溺れることなく、見事に織り上げてみせた。とりわけ、母親と娘の再度の別れのシークエンスが激しく胸を打つ。
-
お早よう
制作年:
松竹の伝統である下町喜劇、長屋喜劇の舞台を郊外の建売住宅地に移した、小津のユーモアセンスの冴えわたった傑作。10軒ほどの家が建ち並ぶ住宅地に住む人々ののどかな日々をスケッチ風に描写。小津安二郎が多くとり上げた、親子、兄弟、夫婦間の葛藤というテーマはここではそれほど深く堀り下げられることはなく、タイトルのように日常のあいさつや平凡な会話を通し、庶民の生活がいきいきと浮かんでくる。「生れてはみたけれど」を思わせる兄弟が登場して、いたずらしたり、父親にテレビをねだったり……。最後にテレビを買ってもらった弟が唐突にまわすフラフープのおかしさ!
最新ニュース
おすすめフォト
おすすめ動画 >
-
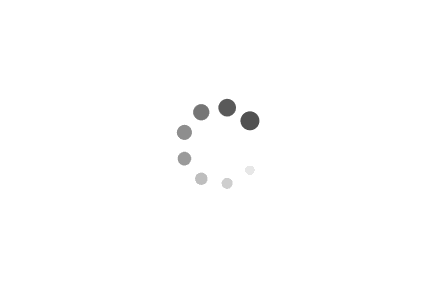
X
-
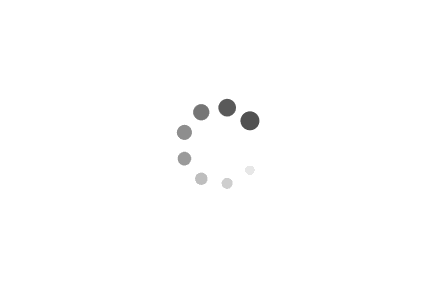
Instagram