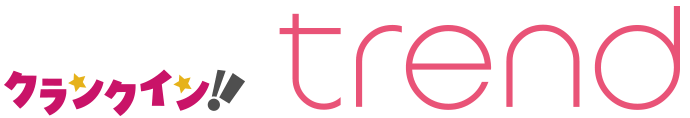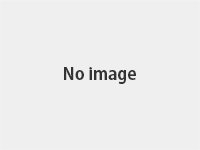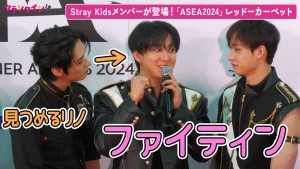本多猪四郎
本多猪四郎 出演映画作品
-
空の大怪獣ラドン〈4Kデジタルリマスター版〉
制作年:2022年12月16日(金)公開
『ゴジラ』シリーズに並ぶ、東宝怪獣映画の代表作を4Kデジタルリマスター版として上映する。核実験と異常気象で突然変異した太古の翼竜プテラノドンが阿蘇山から出現し、福岡へ襲来する。『ゴジラ〈1954年〉』の本多猪四郎監督がメガホンをとり、円谷英二が特撮技術を担当する。出演は佐原健二、白川由美、小堀明男、平田昭彦、田島義文ら。
-
モスラ 4Kデジタルリマスター版
制作年:2021年12月10日(金)公開
本多猪四郎が監督を務め1961年に公開された、ザ・ピーナッツが歌うテーマソングもお馴染みの特撮怪獣映画が、4Kデジタルリマスター版でスクリーンに帰ってくる。島に住む小美人とテレパシーで通じ合う守護神として描かれるモスラは、それまでのゴジラをはじめとした人類と対立する存在だった“怪獣”の概念を180度変えるものとなった。
-
ゴジラ 60周年記念デジタルリマスター版
制作年:2014年6月7日(土)公開
1954年に公開された特撮怪獣映画の金字塔を最新のデジタル技術で修復。映像と音声のクオリティを公開当時の状態に近づけたデジタルリマスター版。当時960万人を動員する大ヒットとなり、ハリウッド版リメイクの最新作に至るまで継承され続けている原点に触れるまたとないチャンス。東京が滅ぶイメージのインパクトはいまなお鮮烈だ。
-
ゴジラ 60周年記念デジタルリマスター版
制作年:2014年6月7日(土)公開
1954年に公開された特撮怪獣映画の金字塔を最新のデジタル技術で修復。映像と音声のクオリティを公開当時の状態に近づけたデジタルリマスター版。当時960万人を動員する大ヒットとなり、ハリウッド版リメイクの最新作に至るまで継承され続けている原点に触れるまたとないチャンス。東京が滅ぶイメージのインパクトはいまなお鮮烈だ。
-
フランケンシュタインの怪獣 サンダ対ガイラ 海外版
制作年:
「怪獣王ゴジラ」とは異なり、もともと日本版と同時に海外用の撮影・編集を行なっているのでストーリーの破綻はない。ラス・タンブリンのナマの声や英語をしゃべる水野久美を楽しめるほか、同じシーンでも、BGMの異なるシーンも多数存在している。英語でのタイトルは“The War of the Gargantuas“。
-
獣人雪男
制作年:
「ゴジラ」の香山滋の原作を得て、日本アルプスを舞台に秘境テーマと雪男伝説をミックスした作品。「ゴジラ」の世界的大成功で意気揚がる円谷英二をはじめとする東宝特撮陣が、総力を結集した意欲作だが、題材的にいささか無理があった。根岸明美が魅力的。
-
緯度0大作戦
制作年:
本多監督と円谷英二特技監督の名コンビによる日米合作のSFアクション映画。“緯度0”という海図にない海底のユートピアの平和を守る主人公たちが、世界征服をたくらむ悪の天才科学者と壮絶な死闘を展開する。盛りだくさんの内容ながら、円谷英二の特撮が不調で失敗作に終わった。
-
怪獣大戦争
制作年:
ゴジラ、ラドン、キングギドラが、超科学力で地球侵略を計るX星人の手でコントロールされ地球各地を暴れ回る。前作「三大怪獣 地球最大の決戦」で最大限の効果を上げた怪獣バトルロイヤルを宇宙規模まで拡大し、スケール・アップを狙った意欲作。
-
ゴジラ〈1954年〉
制作年:
田中友幸製作、本多猪四郎監督、円谷英二特技監督という東宝特撮映画の黄金トリオによる日本初の特撮怪獣映画で、内外の特撮映画に多大な影響を与えた記念碑的な名作である。相次ぐ水爆実験により太古の眠りから覚めた体長50メートルに及ぶ大怪獣ゴジラは、口から放射能線を吐き東京を焼土と化す。しかし芹沢教授が発明した水中酸素破壊剤(オキシジェン・デストロイヤー)の前にさしものゴジラも敗れる。当時、普通作品の直接製作費が1本・2千万円の頃に約6千万円をかけ、撮影日数も4ヵ月に及ぶ超大作で、空前の大ヒットを記録した。またこの作品は日本映画では初めて1956年ニューヨークの一流劇場でロードショー公開され、これまた大ヒットを記録するという快挙を演じた。以降東宝の特撮映画はほとんどアメリカで公開されている。なお、「ゴジラ」のアメリカ版はレイモンド・バー扮する新聞記者の部分が撮り足され細部を改編、「怪獣王ゴジラ」のタイトルで公開された。
-
キングコング対ゴジラ
制作年:
前作「ゴジラの逆襲」から7年を経て甦ったゴジラが、アメリカを代表するモンスター、キングコングと大格闘を展開する。北極の氷が溶け再び甦ったゴジラは、その帰巣本能から一路日本へ向かう。一方、南海ファロ島からTV局の手で眠らされ日本へ運ばれるキングコングは、近海で眠りから覚め日本へ上陸する。折から上陸していたゴジラは日光・中禅寺湖付近で衝突し……。東宝創立30周年記念映画として製作された、当時としては空前の超大作。日米を代表するモンスターであるゴジラとキングコングを対決させるというアイデアが大衆にアピールした。
-
妖星ゴラス
制作年:
重力が地球の6000倍の黒色妖星・ゴラスが地球に接近し、地球と衝突するまで、あと2年。道は二つ、“ゴラスの軌道を変えるか、地球が逃げるか”だ。人類は後者の道をとり、南極に巨大なジェット噴射口を作って、40万キロ地球を移動させようとするが……。壮大なストーリーを映画化したSF大作だ。この映画が製作された前年、ガガーリンを乗せた初の有人人工衛星が打ち上げられ、世は宇宙時代に突入。それを反映してか、物語もハードSFとして緻密に練りあげられている。東宝お得意の怪獣は、南極の基地建設を妨害するマグマが登場するが、全編のなかでは添え物といった感じで、この作品の見どころは、異常気象によって水没する世界の国々や、500坪にわたる壮大な南極セットなど、そのミニチュア特撮にある。“怪獣プロレス”ものと違い、日本では珍しい破天荒なストーリーとSFマインドを併せ持った特撮映画として、再評価が望まれる作品である。
-
美女と液体人間
制作年:
核実験による放射能の影響で、ゼリー状になった“液体人間”。下水道を通って東京に現れた液体人間は、人々を次々に液体化していく。サスペンスあふれる導入部から、液体人間が火の海で絶命するラスト・シーンの悲愴感まで、息をもつかせぬ展開が光る、東宝特撮映画の名作。ドラマ部分と特撮部分の見事な融合が、成功した大きな要因である。単なる怪物ではなく、恋する男として液体人間を描いているあたりも涙を誘う。
-
キングコングの逆襲
制作年:
北極の極点近くに眠る核物質・エレメントXを発掘するため、ロボット怪獣メカニコングを開発したドクター・フー。しかしその計画は失敗し、彼は本物のキングコングを使おうとする……。後半、東京に上陸したキングコングと、それを追ってきたメカニコングとの、東京タワーでの死闘が見もの。この東京タワー、実際に鉄骨を組み上げて作り、重量感あふれる出来になっている。特技監督・円谷英二は、本家「キングコング」(1933・米)への思い入れが強く、コングがゴロザウルスと戦うシーンでは、本家のコングと恐竜との死闘とまったく同じカット割りで撮影した。出演陣では、ドクター・フー役の天本英世がマッド・サイエンティストを巧演。東宝35周年を記念して作られた作品。
-
地球防衛軍
制作年:
本多猪四郎監督と円谷英二特技監督の名コンビによる東宝初の本格的SF映画。地球征服をもくろむ宇宙人ミステリアンは、前線基地として富士山麓に巨大な半球形の白色ドームを建設するが、地球側も地球防衛軍を組織して対抗する。ミステリアンのドームの円盤、地球防衛軍の数々の科学兵器の大攻防戦が繰り広げられる。東宝はすでに「ゴジラ」の成功で特撮映画の王道を走っていたが、「禁断の惑星」や「宇宙水爆戦」といったアメリカ製の本格的SF映画に刺激され、総天然色シネマスコープによる空想科学映画として製作された。この映画が公開された年、国産ロケット第1号の打ち上げが成功し、ソ連のスプートニク1号が地球の周回軌道に乗り、夢物語であった宇宙時代が幕を開けた。小松崎茂デザインによる超科学兵器が次々と惜しげもなく登場し、円谷英二の乗りに乗った特撮シーンのみだれ打ちは圧倒的な迫力で、平凡なドラマ部分の不備を補って余りあった。「ゴジラ」とともに日本SF映画史上のターニング・ポイントとなった秀作である。伊福部昭が音楽を担当している。
-
三大怪獣 地球最大の決戦
制作年:
5000年前に地球に飛来し、地球人と同化したらしい謎の金星人予言者によって、不思議な出来事が次々と予言されていく。九州・阿蘇の火口からはラドンが、横浜港沖ではゴジラが、そして黒部渓谷の霞沢に落下した隕石からは地球を滅ぼしにやって来たキングギドラが現れ、それぞれ東京に向かう。この危機に防衛大臣は、インファント島の小美人にモスラの協力を要請、モスラはゴジラとラドンを説得し、一致団結してキングギドラに闘いを挑むのだが……。シリーズ中“最強の敵”といわれるキングギドラが、縦横無尽に暴れ回る痛快怪獣映画。対決シーンは大迫力。
-
モスラ〈1961年〉
制作年:
「空の大怪獣ラドン」でリアルな怪獣映画の一つの到達点をきわめた東宝特撮陣は、以降怪獣もの以外のSFジャンルに挑戦するが、興行的に苦戦し、安定路線として怪獣映画の本格的な復活が図られた。かくて怪獣映画初のカラー・ワイド画面による「モスラ」が東宝特撮映画の黄金トリオの手により製作された。南海の幻想的なインファント島にやって来た悪徳ブローカーは、身長30センチの小美人を誘拐し東京でショーを開催して巨利を得る。しかし、捕われた小美人のSOSテレパシーに呼応して守護神・巨大蛾モスラが東京に上陸する……。東京タワーに寄りかかってサナギから成虫へと変態する場面は、あまりにも有名。またザ・ピーナッツの歌う『モスラの歌』は、東宝怪獣シリーズの挿入歌として不滅の曲だ。なお、この作品は「ゴジラ」のようなリアルな怪獣ものとは違いファンタジックな要素にあふれた怪獣ものとして企画された。3人の純文学者によって原作が書かれた点も記したい。
-
マタンゴ
制作年:
プチブルの若い坊ちゃんたちがヨットで遭難。漂着した孤島で体験する恐怖を描くホラー映画。登場人物を7人に限定して、さらに鳥も動物もいない無人の孤島という一種の“密室”に舞台を設定した中で、極限状況に追い込まれたエゴむき出しの人間ドラマが展開する。やがて7人を襲ってくる飢餓と、幻惑的な味覚を持ちながら、食べると自らもキノコとなってしまう怪キノコ・マタンゴの誘惑との相剋。メンバーが次々とマタンゴとなっていくにしたがい、サスペンスがふくらんでいく。また、イーストマンカラーを生かした、毒々しいマタンゴの極彩色も不気味な感じを盛り上げている。クライマックスのゾンビのように迫ってくるマタンゴの群れ、そしてアッと驚くラストは必見。
-
メカゴジラの逆襲
制作年:
前作でゴジラに敗れ去ったメカゴジラが、今回は主役のゴジラを押しのけタイトルロールとして復帰。ブラックホールの第3惑星人はメカゴジラを再建造し、さらに新怪獣チタノザウルスを仲間にして逆襲に転じるのだった。メカゴジラの強烈なキャラクターにゴジラは今回も圧倒される。
-
お嫁においで
制作年:
弾厚作(加山のペンネーム)の同名のヒット曲をもとに松山善三が脚本を担当、怪獣映画の大御所・本多猪四郎が演出にあたる青春映画。父の経営する造船会社に働く加山雄三と、タクシーの運転手・黒沢年男の恋の獲得作戦。加山の妹役の内藤洋子が兄に加勢し、ついに加山はプロポーズするが……。ヒット曲『夜空を仰いで』も挿入される楽しい一編。
-
モスラ対ゴジラ
制作年:
「キングコング対ゴジラ」の空前の大ヒットの夢よもう一度とばかりに企画された一編。名古屋にほど近い干拓地から突然ゴジラが出現し、名古屋市内へ乗り込み破壊の限りを尽くす。正義の怪獣モスラは日本を守るためにゴジラに闘いを挑む。ゴジラがデビュー作をしのぐ徹底した凶暴な悪役ぶりをみせ、モスラの成虫及び幼虫と死闘を演じる。この作品でゴジラの悪のイメージは終わり、以降のシリーズではモスラをしのぐ正義の怪獣として、地球の平和を乱す宇宙人や怪獣と激闘を展開することになる。“ゴジラ”シリーズの一つの転換期を示す作品。
-
フランケンシュタインの怪獣 サンダ対ガイラ 海外版
制作年:
「怪獣王ゴジラ」とは異なり、もともと日本版と同時に海外用の撮影・編集を行なっているのでストーリーの破綻はない。ラス・タンブリンのナマの声や英語をしゃべる水野久美を楽しめるほか、同じシーンでも、BGMの異なるシーンも多数存在している。英語でのタイトルは“The War of the Gargantuas“。
-
フランケンシュタイン対 地底怪獣(バラゴン)
制作年:
東宝とベネディクト・プロ提携による初の日米合作怪獣映画。第二次世界大戦末期、ナチスドイツから秘密裡に日本に運び込まれたフランケンシュタインの怪物の心臓は広島に到着したが、原爆で行方不明となる。15年後、人間化して異常成長を遂げたフランケンシュタインは、折から出現した地底怪獣バラゴンと対決する。海外ホラーの古典的キャラクター“フランケンシュタイン博士の怪物“を主役に迎え、それを巨大化して怪獣と対決させるという着想が実にユニークである。しかし本家フランケンシュタインが科学の力によって作られた再生人間であるのに対して和製フランケンシュタインの方は、一個の心臓から巨大に成長するクローン人間であり、容貌と名前以外に共通性はほとんどない。ビデオ、DVDには初公開時のエンディングを収録。
-
太平洋の鷲
制作年:
本多猪四郎監督が特殊技術監督・円谷英二と組んで作った、戦後初の本格的戦争スペクタクル。のちにこのコンビは、特撮怪獣映画を数多く生み出していく。連合艦隊司令長官・山本五十六の悲劇を中心に、太平洋で空母赤城、加賀などを次々に撃沈され、敗戦の色が濃くなっていく日本軍を描く。
-
怪獣王ゴジラ
制作年:
英語タイトルは“Godzilla King of the Monsters“。「ゴジラ」アメリカ公開に際し、海外で新しく撮り足したシーンを付け加えて再編集された改作版。アメリカの新聞記者がゴジラの東京上陸をレポートするという内容に変更された。そのため、物語の細部は縮まり、ゴジラの破壊性が強められている。
-
怪獣王ゴジラ
制作年:
英語タイトルは“Godzilla King of the Monsters“。「ゴジラ」アメリカ公開に際し、海外で新しく撮り足したシーンを付け加えて再編集された改作版。アメリカの新聞記者がゴジラの東京上陸をレポートするという内容に変更された。そのため、物語の細部は縮まり、ゴジラの破壊性が強められている。
-
さらばラバウル
制作年:
本多猪四郎の、「ゴジラ」の前作にあたる戦争メロドラマで、当時流行した戦争歌謡、『ラバウル小唄』に絡めた企画。太平洋戦争末期、ラバウル駐在の航空隊で鬼隊長と呼ばれた若林大尉を中心に、彼と看護婦すみ子のロマンスなどを織り込んで、敗色濃い戦地の悲惨さを描いている。特殊技術は、円谷英二。
-
決戦! 南海の大怪獣 ゲゾラ・ガニメ・カメーバ
制作年:
銀河の彼方からやって来た宇宙生物が、イカ、カニ、カメに乗り移って、ゲゾラ、ガニメ、カメーバの3匹の怪獣と化した。南洋の孤島にやってきた日本の生物学者たちは怪獣たちに遭遇し、凄絶な戦いに巻き込まれる。怪獣のデザインが少々安易。ビデオタイトルは「ゲゾラ・ガニメ・カメーバ 決戦! 南海の大怪獣」。
-
宇宙大戦争
制作年:
超低温下で重力がなくなる“冷却線“を使って、宇宙人・ナタールが地球侵略を開始した。地球の各地では、鉄橋が光りながら空中へ浮き上がったり、汽船が山に激突したり、海が凍って空に逆流したりと奇怪な事件が次々に起こる。科学者たちのグループは冷却線の攻撃に対抗すべく、熱線砲を開発、彼らの基地があると思われる月へと向かうが……。熱線砲を抱えて月へ出発するスピップ号、途中出くわす宇宙ステーション、そしてナタールの円盤群など、宇宙空間を舞台に特技監督・円谷英二の腕が全編に冴えわたったSF映画。1959年の製作とは思えない凝ったディテールと凄まじいアクションが魅力。
-
宇宙大怪獣ドゴラ
制作年:
宇宙から飛来したナゾのクラゲ状半透明の怪物・ドゴラが地球を襲った。地上の電気を吸い上げエネルギーとするこの怪物のために、都市や海上の船などは壊滅状態となる。半透明の怪獣のため、従来のぬいぐるみでは表現できない特撮がユニーク。特技監督は円谷英二。
-
怪獣総進撃
制作年:
昭和29年の「ゴジラ」でスタートした東宝の怪獣映画シリーズは、「モスラ」や「妖星ゴラス」などの傑作を生み出し、また「大怪獣ガメラ」や「大巨獣ガッパ」など他社の怪獣ものにも影響を与え、海外にも多くのゴジラ・フリークを生み出した。しかしそのマンネリ化は防ぎようもなく、昭和40年代に入ったあたりから初期の頃のヒューマンな味わいが薄れ、怪獣同士の戦いがメインの子供向け作品に移行していく。この作品はそれまでの東宝怪獣キャラクターが勢ぞろいして怪獣島に管理され、平和な生活を送っているという状況で物語が始まる。そこに宇宙から凶悪怪獣キングギドラが飛来し、地球怪獣との死闘が……。
-
海底軍艦
制作年:
日本SF小説界の草分け的存在である押川春浪の同名小説を原作とした作品。1万2千年も前に地球上で繁栄を誇ったムウ帝国は、地殻変動のために海底に沈没した。しかし彼らはその科学力で海底に都市を築き上げて世界征服を企んでいるのだ。旧日本海軍の知能と技術を集結した“海底軍艦“は、ムウ帝国の野望を阻止すべく、海底深く戦いを挑んでいく。しかし、行く手には全長150メートルもある大怪竜のマンダが待ちかまえていた……。艦首に穿孔器をつけた海底軍艦のデザインは、まるでブリキのおもちゃのようにゴツゴツしていて楽しい。東宝の“怪獣“ものが最もノッていた時期の佳作である。特技監督は円谷英二。
-
フランケンシュタインの怪獣 サンダ対ガイラ
制作年:
「フランケンシュタイン対地底怪獣」の姉妹編。クローン生物のフランケンシュタインが、より怪獣的になり、分裂によって山の怪獣サンダと海の怪獣ガイラの2体に分かれる。心優しい兄のサンダと人間を食う凶暴な弟のガイラが、骨肉相食む死闘を演じる。2匹の死闘は都市を中心に展開され、従来脇役に徹してきた自衛隊が、今回は生命の細胞までも焼きつくす殺人光線兵器・メーサー光線砲戦車を登場させ、互角の闘いを演じる。この日・米合作によるフランケンシュタイン2部作は、当時の怪獣ブームから、人間不在の怪獣トーナメント化した怪獣映画に一石を投じたが、本流にはならなかった。
-
フランケンシュタインの怪獣 サンダ対ガイラ
制作年:
「フランケンシュタイン対地底怪獣」の姉妹編。クローン生物のフランケンシュタインが、より怪獣的になり、分裂によって山の怪獣サンダと海の怪獣ガイラの2体に分かれる。心優しい兄のサンダと人間を食う凶暴な弟のガイラが、骨肉相食む死闘を演じる。2匹の死闘は都市を中心に展開され、従来脇役に徹してきた自衛隊が、今回は生命の細胞までも焼きつくす殺人光線兵器・メーサー光線砲戦車を登場させ、互角の闘いを演じる。この日・米合作によるフランケンシュタイン2部作は、当時の怪獣ブームから、人間不在の怪獣トーナメント化した怪獣映画に一石を投じたが、本流にはならなかった。
-
ガス人間第1号
制作年:
美しい踊りの家元・藤千代に惚れ、彼女のために悪事を働くガス人間。この狂行をやめさせようと岡本警部補(三橋)は、藤千代の手を借りようとするが……。1954年の「透明人間」に始まり「美女と液体人間」(1958)、「電送人間」(1960)、「マタンゴ」(1963)と続く東宝SF路線・変形人間ものの一編。円谷英二が特殊技術を担当し、人間がガスに変貌する過程をリアルに表現。ライターでガス人間が爆発するラストも面白い。
-
大怪獣バラン
制作年:
ムササビからヒントを得たような大怪獣が活躍する一編。湖底から現れるスローモーションのカットや、山中で主人公たちを襲う場面など、出色の出来。脚本を担当した関沢新一は石井輝男とともに清水宏に師事した門下生。大詰め、羽田沖から都内へ上陸しようとするバランと、それを阻止しようとする自衛隊の攻防が見ものだ。
-
空の大怪獣ラドン
制作年:
東宝が「ゴジラ」を凌ぐ2億円(うち特撮費は1億2千万円)の巨費を投じて製作した日本初のカラー怪獣映画の力作。大気中の放射性元素の増加により、阿蘇の地下洞窟に卵のまま眠っていた太古の翼手竜ラドンが孵化し、地震による大陥没地から地上へ飛び出して……。ラドンの登場シーン、ジェット戦闘機隊との大空中戦、福岡市内の破壊シーン、そしてラストの阿蘇山噴火によるラドンの最期と、終生航空映画を作ることを夢見ていた円谷英二の大空への憧れが十二分に発揮されており、名特撮シーンがたっぷり盛り込まれている。本多猪四郎監督は特撮とドラマのスピーディーなカッティングを心がけ、かつてないスピード感あふれる怪獣映画に仕上げた。
-
怪獣総進撃
制作年:
昭和29年の「ゴジラ」でスタートした東宝の怪獣映画シリーズは、「モスラ」や「妖星ゴラス」などの傑作を生み出し、また「大怪獣ガメラ」や「大巨獣ガッパ」など他社の怪獣ものにも影響を与え、海外にも多くのゴジラ・フリークを生み出した。しかしそのマンネリ化は防ぎようもなく、昭和40年代に入ったあたりから初期の頃のヒューマンな味わいが薄れ、怪獣同士の戦いがメインの子供向け作品に移行していく。この作品はそれまでの東宝怪獣キャラクターが勢ぞろいして怪獣島に管理され、平和な生活を送っているという状況で物語が始まる。そこに宇宙から凶悪怪獣キングギドラが飛来し、地球怪獣との死闘が……。
-
恋化粧
制作年:
今日出海原作『君死に給うことなかれ』の映画化。1954年、日本初のSF大作「ゴジラ」を大ヒットさせた本多猪四郎が、その次回作として撮り上げた作品。とはいえ、これは特撮ものではない純然たる文芸映画。自分の会社の自動車盗難事件の犯人を追う力彌と、彼を慕う芸者・初子の恋の行方を描いている。
最新ニュース
おすすめフォト
おすすめ動画 >
-
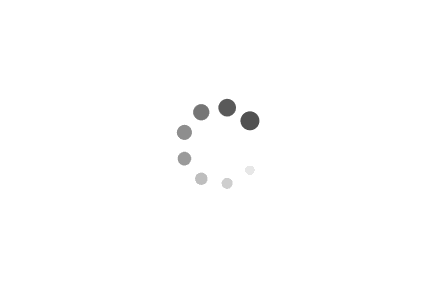
X
-
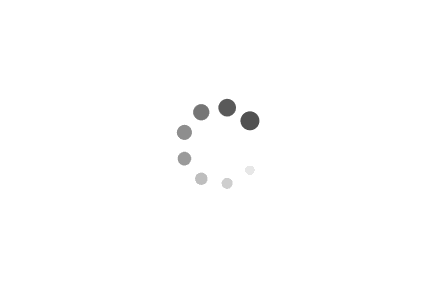
Instagram